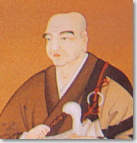 (1341年〜1420年) 三日月上人 常陸国久慈郡巖瀬(現在の茨城県那珂郡大宮町上岩瀬)の城主白石志摩守宗義の子として誕生、幼名を文殊丸。 5歳の時、父宗義が戦で非業の死を遂げ、その3年後、父の菩提を弔うために瓜連常福寺・了実上人に就き出家し、名を聖冏と改めた。上人はもとより聡明なお方であったが、尚一層のご修行と勉学に励み、広く仏教全般を学ばれ、更には神道・和歌にも深く通じた。残された著作は百巻を越え、特に「選択伝弘決疑鈔直牒」十巻は、応永3年(1396)に起こった「佐竹氏の乱」を避け阿弥陀山(不軽山ともいう)の洞穴に身を隠し、干し柿を食べて飢えを凌ぎ、洞穴の滴を硯に受けて撰述されたものである。 聖冏上人当時の浄土宗は、「寓宗」「附庸宗」と呼ばれ、未だ独立した宗として認められてはいなかった。それを嘆かれた聖冏上人は伝法を確立し、現在の浄土宗の基礎を築いた。 晩年、弟子の聖聡上人(増上寺開山)の請いにより小石川に草庵を結んで移り住み、念仏教化の日々をお過ごしになられ、応永27年(1420)9月27日、80歳でご往生された。 上人は額に「三日月」の相があったという言い伝えから「繊月禅師」とも称され、「繊月会館」の名称は聖冏上人の遺徳を現代に顕彰するために命名された。 |